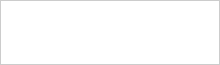このページの内容
建設業許可の3つのメリット
建設業許可を取得するメリットは、経営者や会社の方針、考え方・目的によって様々だと思います。
ただ私が、
『大手電設会社で施工管理をしてきた経験』
『行政書士として建設業許可申請を承ってきた経験』
から考えると、
次の3つが共通する本当のメリットを思っております。
1 建設業許可があれば請負代金500万円以上の工事が受注できる
これは、建設業法施行令第1条の2で明確に規定されております。
因みに、この500万円は、消費税込(消費税込み)の金額です。
逆に考えると・・・・
建設業の許可がなくても請負代金500万円以下の工事は受注できるということです。
でも・・・500万円未満の工事しかできないって・・・やり辛いですよね??
それに、お施主様や元請から500万円以上の仕事の話しが来ても、建設業許可が無いから断らざる得ない・・・のはちょっともったいないですね。
私が大手電設会社にいた経験でいうと・・・
500万円未満の雑件改修工事などの担当となると・・・
利益を出しやすいA材(変圧器、大きな設備)が持てない場合が多いので、
B材(細かい建材)と工数・歩掛けのみシビアな状態となって、ケッコウ辛かった思い出があります。
つまり500万円未満となると・・・当然売上は下がり、粗利も下がり、経営が苦しくなる。
やはり、売上規模を上げることは、経営を安定する意味で非常に重要なことだと言えます。
したがって、売上規模を上げるには、建設業許可は必要と言えます。
2 協力業者(下請け業者)選定の条件
また、最近は建設業許可をもっていることを発注条件とする元請も多くなってきました。
例えば・・・一つイメージしてください・・・
『もしあなたが、元請の施工管理担当者として・・・建設業許可を持っていない会社に発注できるか??』
私も大手電設会社で、現場の工事主任として施工管理をやっていたころは、会社の協力業者選定ルールに基づいて、協力業者を選定しなければなりませんでした。
つまり、建設業許可業者でなければ発注できなかったのです。
実際には・・・協力業者のランク付けした登録協力業者名簿があり、その名簿からしか協力業者を選定できなかったのです。
もちろん、この登録協力業者に名簿登載する条件として、建設業許可業者が条件でした。
また、建設業許可は、信用上の問題(建設業に本気である)、施工管理上・安全管理上の問題等々をかんがみると、
『建設業許可と持っていない』 = 『1人親方と同じ』
という感じで、協力業者の更に下請けに無許可業者が入っていないかのチェックもさせられたことがありました。
このようなことも考えると、
やはり、これからは工事を受注するための、一つの営業ツールとして建設業許可は必須であると言えます。
3 経営事項審査(経審)を受ける必須条件
また、現状は、建設業者や建設業に携わる人が、少なくなっている状況なので・・・
① 経審を受審
② 入札参加資格申請
③ 公共工事を受注
という建設業者も少なくなってきている・・・つまり、経審を受ける建設業者が少なくなっている現状では、経審を受けること自体が・・・チャンスです。
つまり、これから公共工事を請けることも、建設業界で生き残るための一つの方策であるとも思います。
もちろん予算的に合わない公共工事も現実的にはあるかもしれませんが、仕事を受注できる可能性を増やすという意味では経審を受審することも大切になってくると思われます。
建設業許可をあきらめないでください!!
弊所では虚偽の書類作成などは承ることはできませんが・・・
弊所の経験やノウハウに従って、事実を詳細に精査したり、様々な角度から要件を検討することによって、許可取得が可能なケースというのは実際には多いのです。
弊所のサービス内容
後見登記されていないことの証明書 の取得(法務局)
身分証明書 の取得(戸籍がある市区町村)
住民票 の取得
納税証明 の取得
事務所の写真撮影
その他諸々・・・取得する書類や作業が多数あります。
更に・・・
申請書類の作成
土木事務所との折衝
申請手続き
・・・etc
すべてお任せください!!